鍛冶町にあった酒場の話
鍛冶町が小さな家が密集した庶民の街から、現在のような飲食街に変貌し始めたのは、昭和30年代後半の頃であったろう。木造の小さな家屋が取り壊され新しい建物が建ったり、あるいは改装されたりそういうことがこの40年間に繰り返されながら、少しずつ現在のような街ができていった。
この話は、鍛冶町が今のような街に変貌し始めるころよりもっと以前の、昭和30年代の初めの頃のことであった。
昭和30年代初め、鍛冶町に1軒の飲食店もない頃、鍛冶町のある一角に七坪の小さなバーが出来た。
カウンターだけの殺風景な店で、カウンターの中に年を取っているのか若いのか風貌からは察しがつかないような男がひとりいた。その男がこの店の主人らしかった。
ただウヰスキーを飲ませるだけの店で、男は客がカウンターの席に座ると、注文など聞かず、ただ黙って小さなグラスにボトルからウヰスキーを静かに注いだ。
男はく妙な癖があって、ウヰスキーをグラスに注いだ後とか、客とボソボソと話をする時、あるいは何かの拍子の時、鼻をクックッと秘かに鳴らして自分の体の臭いを嗅ぐことだった。
昭和30年初めといえば日本が敗戦の痛手から立ち直り始めた時代である。酒場でウヰスキーを飲むなどという発想は一般の人間にはなかったといってよい。だからこの男の店に来る客は、少なかった。
鬱陶しいほど生暖かい雨が降るくらい夜、その店のカウンター席にひとりの男が座った。よれよれの背広にドタ靴、下唇の厚いあまり風貌の良くない男だった。何を話すわけではなく、ただ黙ってウヰスキーをチビリチビリと飲んで帰った。しかし、眼鏡の奥から注がれる、その男の覗き込むような視線が心に焼きついた。
その後、男は何度かその酒場を訪れ、カウンターの中の寡黙な主人は男の覗き込むような視線に引き込まれるようにぽつぽつと話を交わすようになった。
日本の戦後復興の切っ掛けとなった朝鮮戦争が勃発したのは、昭和26年6月26日の夜の事であった。
その朝鮮半島での韓国と北朝鮮の戦争の影響が北九州一帯に出始めたのは、マッカーサーが仁川上陸作戦を敢行してしばらくたった頃からだった。その頃から城野の補給基地は米兵の死体処理上にさま変わりした。戦死した米兵の死体は海峡を越えて運ばれてきた。砂津港の岸壁で今度は貨車積みされると長く連ねた列車で、城野基地の引込み線まで入っていった。甘酸っぱい独特の臭いのする棺を降ろすと、冷房装置のある棟に担ぎ込まれた。棺の通った跡、線路、貨車の中には夥しい数の蛆虫が落ちて這っていた。
遺体の処理は、消毒をし、防腐剤を施し、生前に近い状態に整形した。死体がぶらさげている真鍮の認識プレートを頼りに作業を進めた。取り出した内臓は集めて焼却場で焼いた。
処理が終わると、再び顔の部分に硬質のガラスの窓がある寝棺に納め、別の棟に移し、次から次へと遺体の入った棺をアメリカ本土に飛行機で送った。それでも各棟に安置された棺の数は増える一方だった。
この労役にはほとんど日本人が携わった。報酬が格段に良かった。しかし死体から出るにおいには閉口した。死んだ人間から出る臭いは生きている人間の毛穴から浸み込んでくるのだった。
朝鮮戦争は昭和28年10月に38度線を境界に、休戦という形で終わった。城野基地での米兵死体処置は休戦後も続いたが、いつ終わったのかは定かでない。
鍛冶町の片隅に、小さなバーが出来たのは、朝鮮戦争休戦後、三年ほどたった頃だった。そしてそのバーが二年か三年くらいの短い間だった。世の中が落ち着いてくると、自分の体の臭いをいつも気にするように嗅いでいた、鍛冶町の小さなバーの主人は人知れず店をたたみ、どこかへ去って行った。そして、その小さなバーが鍛冶町のどのあたりにあったのかわからない。
松本清張は朝鮮戦争に送られる黒人米兵の暴動と城野基地での米兵遺体処理を題材にして「告知の絵」
という小説を書いた。
城野基地で起きた黒人米兵暴動事件は、戦後「祇園祭」が再開される日の先日蒸し暑い夜に起きた。その夜暴動を起こした黒人部隊は、朝鮮戦争で全員戦死、城野基地に無残な遺体となって戻ってきた。
( 曽田 新太郎・筆)
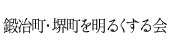

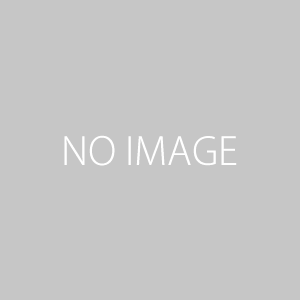




この記事へのコメントはありません。